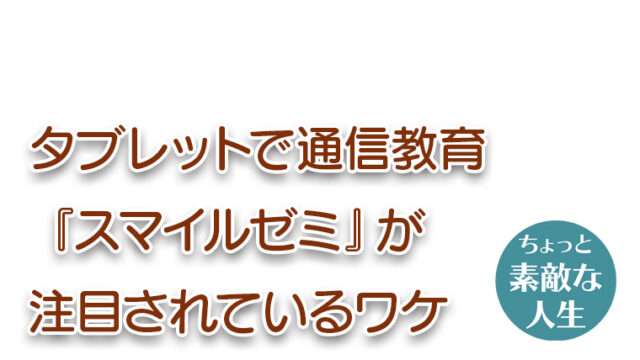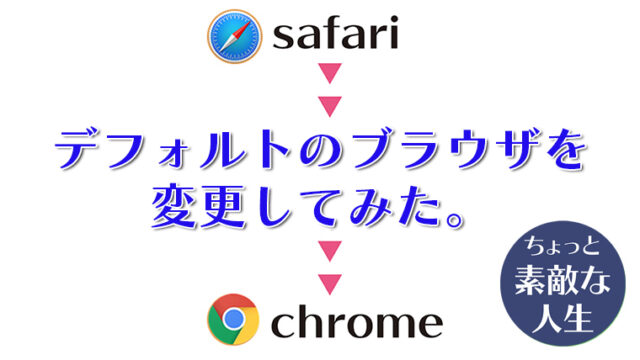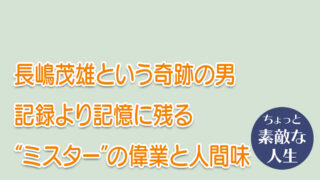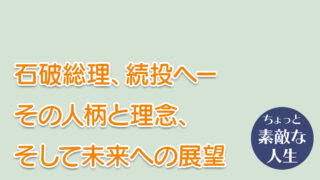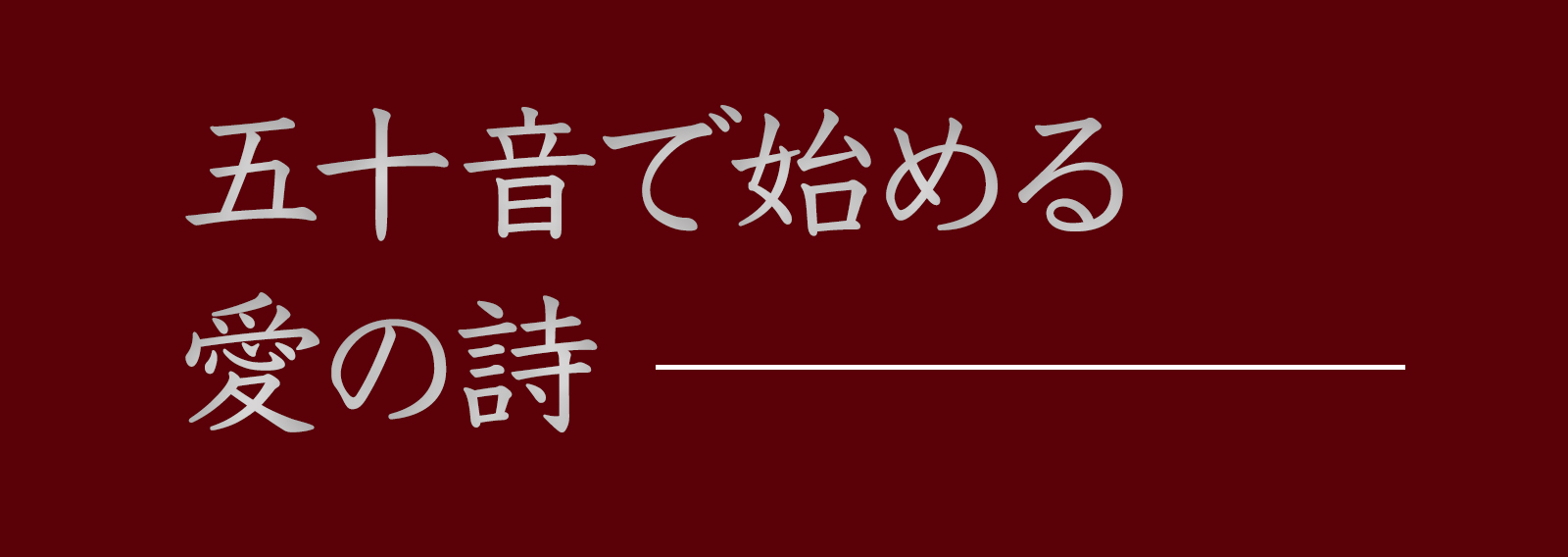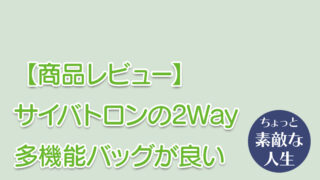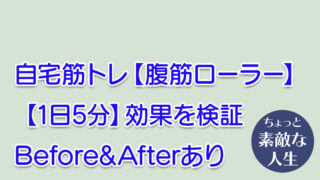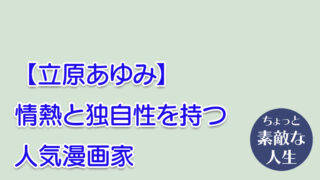高校野球の未来はどこへ向かう?
みなさん、こんにちは。「ちょっと素敵な人生」運営管理者兼ライターのかっつんです。
いよいよ8月が始まりますね。本格的な夏シーズンのスタートです。
さて、8月といえば、8月5日から甲子園球場で第107回全国高校野球選手権大会、いわゆる『夏の甲子園』が開催されます。
高校野球については、選手の健康管理を背景にすでに導入されている投手の球数制限に加えて、新たに7回制やDH制の導入についても議論が始まっているようです。
というわけで今日は「高校野球の未来」について書きます。高校野球の未来はどこへ向かうのでしょうか?

変わりゆく伝統と、新たな可能性
夏の風物詩といえば、「甲子園」と即答する人も多いはず。高校球児たちが全力でプレーする姿に、心を動かされた経験は誰にでもあるでしょう。しかし、今、高校野球は大きな転機を迎えています。
少子化によるチーム数の減少、選手の健康管理の重要性、時代に合わせた指導のあり方、さらにはテクノロジーの導入といった変化の波。伝統と進化の狭間で揺れる「高校野球の未来」について、今回はじっくりと掘り下げてみたいと思います。
少子化と部員不足の現実
少子化の影響は高校野球の現場にも確実に及んでいます。特に地方では、野球部員が9人に満たず試合ができない高校も増えており、「連合チーム」を編成して出場する例が年々増加中。その一方で、サッカーやバスケットボール、eスポーツといった他の競技に興味を持つ子どもたちも増えており、いわゆる“野球離れ”が進行しています。
また、用具や遠征費などのコスト、保護者の送迎負担なども野球部離れの一因とされています。今後は地域との連携や支援体制の強化が鍵となるでしょう。
選手の健康と試合過密の問題
甲子園大会の過密スケジュールは、かねてから問題視されてきました。特に投手の連投による故障リスクは深刻で、「投球数制限」や「1日2試合禁止」などの改革が徐々に進んでいます。
さらに、猛暑の中での長時間プレーも選手の健康にとっては大きなリスク。近年は熱中症対策としてクーリングタイムの導入や、水分補給のルール化も進められています。今後は“安全第一”の観点から大会の運営方法自体の見直しも求められるでしょう。
プロ野球や大学野球では9イニングが標準ですが、高校野球において「7イニング制」導入の議論が近年活発になっています。この背景には、以下のような理由があります。
- 投手の負担軽減(連投リスクの緩和)
- 夏の猛暑による熱中症対策
- 試合時間の短縮と運営効率の向上
すでに一部の地方大会や練習試合では試験的に導入されているケースもあり、「7回まで集中して全力を出し切る野球」への関心が高まっています。伝統との兼ね合いもありますが、未来の甲子園では7イニング制が“新常識”になる日が来るかもしれません。
高校野球では、基本的に全選手が打席に立つ「全員野球」が主流です。しかし、投手の負担軽減や、打撃専門選手の活躍機会を広げる目的で「DH制」導入を求める声も増えてきました。
【DH制導入のメリット】
- 投手が打席に立たずに済み、ケガのリスク軽減
- ベンチの選手にも出場機会が増える
- より戦略的な打順組みが可能になる
高校野球連盟ではまだ本格導入には至っていませんが、今後の選手保護や戦術的多様化を考えるうえで、検討されていく可能性は十分にあります。
この記事に関するお問い合わせやご質問、ご指摘などがありましたら下記フォームへご入力の上、送信してください。
なお、内容によってはご返答までお時間をいただく場合がございます。
あらかじめご了承のほど、よろしくお願い致します。